和光市デンタルオフィス
コラム・ブログ
COLUMN・BLOG
口腔内の細菌とは?〜お口の健康を守るために知っておきたいこと〜
口腔内に存在する細菌の種類
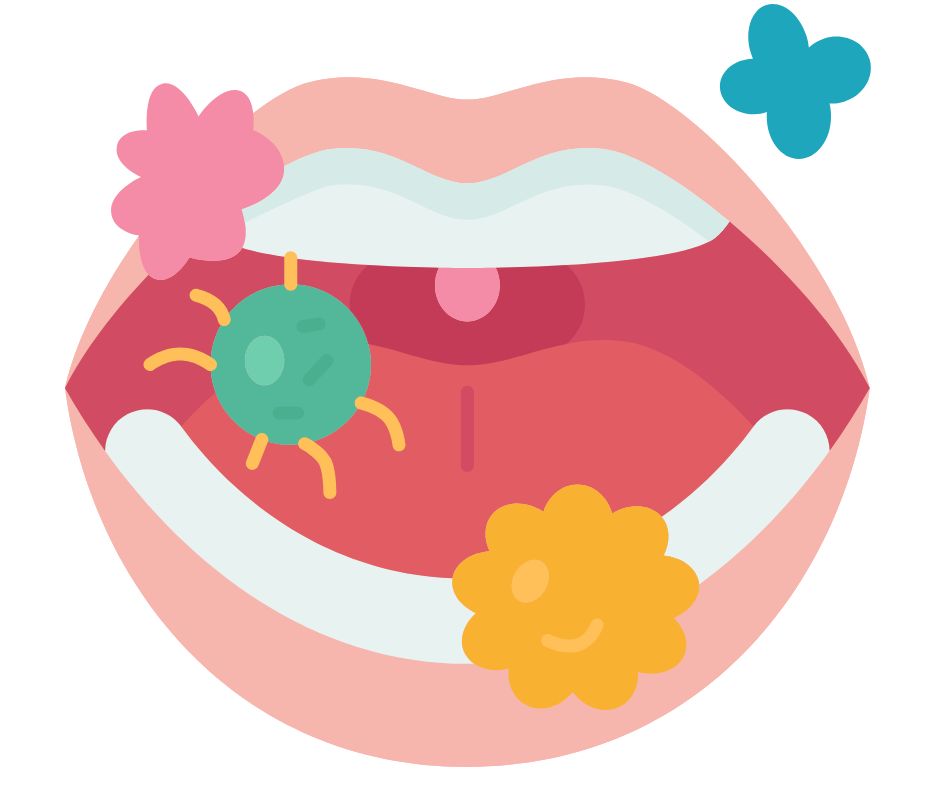
虫歯菌の菌
虫歯の原因となる細菌の中で、特に重要な役割を果たしているのが「ミュータンス菌(Streptococcus mutans)」です。ミュータンス菌は、口腔内のプラーク(歯垢)に多く存在し、糖分をエサにして増殖します。食事やおやつなどで糖分が口の中に入ると、ミュータンス菌はそれを分解して「酸」を作り出します。この酸が歯の表面のエナメル質を溶かし、やがて虫歯へと進行していくのです。
しかし、虫歯はミュータンス菌だけが原因ではありません。例えば「ラクトバチルス菌(Lactobacillus)」も虫歯の進行に関与します。ラクトバチルス菌は酸に強く、歯の表面がすでに傷んでいる状態でも活動できるため、虫歯が進行する段階で特に存在感を増します。初期の虫歯が悪化し、より深い部分へと広がる際に関与する細菌です。
さらに、「アクチノマイセス菌(Actinomyces)」も口腔内に存在する細菌の一種で、特に歯ぐきの近くや歯の根元に潜んでいます。この菌は、根面う蝕(歯の根の部分にできる虫歯)に関与することが知られています。
歯周病の菌
歯周病の原因となる細菌は、主に「嫌気性菌」と呼ばれる、酸素が少ない環境で活動する菌が中心です。その中でも特に重要な役割を担っているのが「ポルフィロモナス・ジンジバリス(Porphyromonas gingivalis)」です。ポルフィロモナス・ジンジバリスは、歯周ポケット(歯と歯ぐきの隙間)が深くなった場所に潜み、歯肉の炎症を引き起こしたり、歯を支える骨を破壊したりする強力な病原性を持っています。
また、「トレポネーマ・デンティコラ(Treponema denticola)」も歯周病に深く関与する細菌です。これは「スピロヘータ」と呼ばれるらせん状の菌で、歯周ポケットの奥深くまで入り込み、組織を破壊する毒素を出すことで歯ぐきの腫れや出血を引き起こします。
さらに、「タネレラ・フォーサイシア(Tannerella forsythia)」という細菌も、歯周病が進行する段階で関与します。この菌は単体での活動はそれほど活発ではありませんが、他の病原性細菌と共に行動することで、歯周組織へのダメージをより深刻にします。
これら3つの細菌は「レッドコンプレックス」と呼ばれ、特に重度の歯周病と深い関係があることが分かっています。
加えて、「フソバクテリウム・ヌクレアタム(Fusobacterium nucleatum)」という細菌は、他の菌とくっつきやすく、歯周病菌同士の結びつきを強める「橋渡し」の役割を果たします。この菌が存在することで、歯周ポケット内に病原性の高い菌が集まりやすくなり、炎症が悪化しやすくなります。
歯周病はこれらの細菌が集団で作り出す「バイオフィルム」という粘着性の膜に守られながら増殖し、通常の歯磨きでは完全に除去するのが難しいのが特徴です。そのため、正しいセルフケアに加えて、歯科医院での専門的なクリーニングや歯石除去がとても重要です。
口臭の菌
口臭に関係する細菌の多くは、口腔内の「嫌気性菌」と呼ばれる、酸素の少ない環境を好む細菌です。これらの細菌は主に舌の表面や歯周ポケット、さらには食べかすが溜まりやすい場所に潜み、口臭の原因となる「揮発性硫黄化合物(VSCs)」という臭いの強いガスを発生させます。
代表的な細菌の一つに「フソバクテリウム・ヌクレアタム(Fusobacterium nucleatum)」があります。この菌は、他の細菌と結びつきやすく、プラークや舌苔(舌の汚れ)に存在し、腐敗臭のような不快なにおいを発生させるのが特徴です。特に、タンパク質を分解して「硫化水素」という卵が腐ったようなにおいを作り出します。
また、「ポルフィロモナス・ジンジバリス(Porphyromonas gingivalis)」も口臭の原因菌として知られています。この菌は歯周病菌の一種で、歯周ポケットの深い部分に潜み、出血や膿を伴う口臭を引き起こすことがあります。
さらに、「プレボテラ・インターメディア(Prevotella intermedia)」は、歯ぐきの炎症が進行している状態で増殖しやすい細菌です。この菌が産生するガスは、特に強い悪臭を放つため、歯周病が進行すると口臭が悪化する要因となります。
舌の表面に多く存在する「ソレイモナス・ムコサ(Solobacterium moorei)」も、口臭との関連が深い菌です。この菌は、舌苔に多く存在し、口腔内のタンパク質を分解して強い口臭を発生させることが知られています。
全身の健康に影響を及ぼす可能性

口腔内の細菌は、単に虫歯や歯周病を引き起こすだけでなく、全身の健康にも深く関わっていることが分かっています。特に、誤嚥性肺炎や心疾患といった命に関わる病気の発症リスクを高めることが指摘されています。
誤嚥性肺炎は、高齢者に多く見られる病気で、食べ物や唾液が誤って気管に入ってしまうことで発症します。健康な人は異物が入るとすぐに咳をして排出できますが、加齢や病気によってその反応が鈍くなると、口腔内の細菌が気管や肺に入り込んで感染を引き起こすのです。特に、歯周病菌である「ポルフィロモナス・ジンジバリス(Porphyromonas gingivalis)」や「フソバクテリウム・ヌクレアタム(Fusobacterium nucleatum)」などは、肺の組織に感染しやすく、肺炎の悪化を促すと考えられています。口腔ケアをしっかり行うことで、これらの細菌の量を減らし、誤嚥性肺炎のリスクを大幅に抑えられることが研究でも明らかになっています。
また、心疾患との関係も重要です。歯周病が進行すると、歯ぐきの炎症部分から細菌が血管内に侵入することがあります。血管内に入り込んだ「ポルフィロモナス・ジンジバリス」や「トレポネーマ・デンティコラ(Treponema denticola)」は、動脈硬化を引き起こす物質を作り出し、血管の壁にダメージを与えることが知られています。これにより、血栓ができやすくなり、狭心症や心筋梗塞といった重大な疾患につながる恐れがあります。
さらに、糖尿病とも深い関係があります。歯周病が進行すると、炎症物質が血液中に流れ込み、血糖値のコントロールを妨げることが分かっています。逆に、糖尿病が悪化すると免疫力が低下し、歯周病がさらに進行するという「負のループ」に陥ることもあります。
口腔内細菌を減らす正しい口腔ケア

口腔内の細菌を効果的に減らし、お口の健康を守るためには、正しい口腔ケアが欠かせません。ポイントは、「細菌を落とす」だけでなく、「細菌が増えにくい環境を作る」ことです。
まず、基本となるのが歯磨きです。歯磨きは、1日に最低2回、特に就寝前はしっかりと行うことが重要です。夜の間は唾液の分泌が減少し、細菌が繁殖しやすくなるため、寝る前にプラーク(歯垢)をしっかり落とすことが効果的です。歯ブラシは、毛先が歯と歯ぐきの境目にしっかり当たるように意識し、軽い力で小刻みに動かすのがコツです。
さらに、デンタルフロスや歯間ブラシを併用することで、歯と歯の隙間に潜む細菌を取り除けます。歯ブラシだけでは届きにくい部分にプラークが残りやすいため、これらの補助清掃用具を毎日のケアに取り入れることが理想的です。特に歯周病が気になる方は、歯間ブラシの使用が効果的です。
次に、舌のケアも大切です。舌の表面には「舌苔(ぜったい)」と呼ばれる汚れが付着し、これが細菌の温床となることがあります。専用の「舌ブラシ」を使い、奥から手前に向かって軽くこするように清掃すると、効果的に舌苔を取り除けます。ただし、強くこすりすぎると舌の粘膜を傷つけるため、やさしく行うのがポイントです。
また、うがいも細菌対策に役立ちます。食後や口が乾いたときには、水で軽くすすぐだけでも口腔内の細菌や食べかすが流され、口臭の予防につながります。さらに、殺菌成分を含むうがい薬を活用することで、歯磨きだけでは取り切れなかった細菌の抑制に効果的です。ただし、うがい薬は歯磨きの代わりにはならないため、補助的に使用するのが理想です。
加えて、唾液の分泌を促すことも重要です。唾液には、口腔内の細菌を洗い流し、抗菌作用を発揮する働きがあります。ガムを噛む、よく噛んで食事をする、こまめに水分補給を行うといった習慣が、唾液の分泌を促進します。特に高齢者やお口の乾燥が気になる方は、意識的に取り入れると良いでしょう。
定期検診を受けましょう

口腔内細菌を減らすには歯科医院での定期検診も欠かせません。毎日のセルフケアでは取りきれない歯石や頑固なバイオフィルムは、歯科医院でのクリーニングによってしっかり除去できます。特に歯周ポケットの奥深くに潜む細菌は、専門的な器具でないと除去が難しいため、定期的な受診が効果的です。
これらのケアを組み合わせることで、口腔内の細菌の繁殖を防ぎ、健康な口腔環境を維持することができます。毎日の習慣を見直しながら、無理なく続けられる方法を取り入れるのが、効果的な口腔ケアのポイントです。
当医院では患者様一人一人に合ったケアを提案し実施しています。
ぜひ定期検診にいらしてください。
カテゴリ
- 虫歯 (39)
- 歯周病 (24)
- 小児歯科 (11)
- 矯正歯科 (28)
- 口腔外科 (12)
- 親知らず (4)
- 顎関節症 (7)
- 噛み合わせ異常 (11)
- マイクロエンド (5)
- セラミック (28)
- インプラント (17)
- 小児矯正 (15)
- マウスピース矯正 (37)
- ワイヤー矯正 (28)
- 部分矯正 (22)
- ホワイトニング (27)
- デンタルエステ (37)
- デンタルIQ (101)
- スタッフブログ (93)
アーカイブ
- 2025年3月 (5)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (4)
- 2024年8月 (5)
- 2024年7月 (4)
- 2024年6月 (5)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (4)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (6)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (6)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (5)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (6)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (5)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (12)
- 2021年8月 (1)






